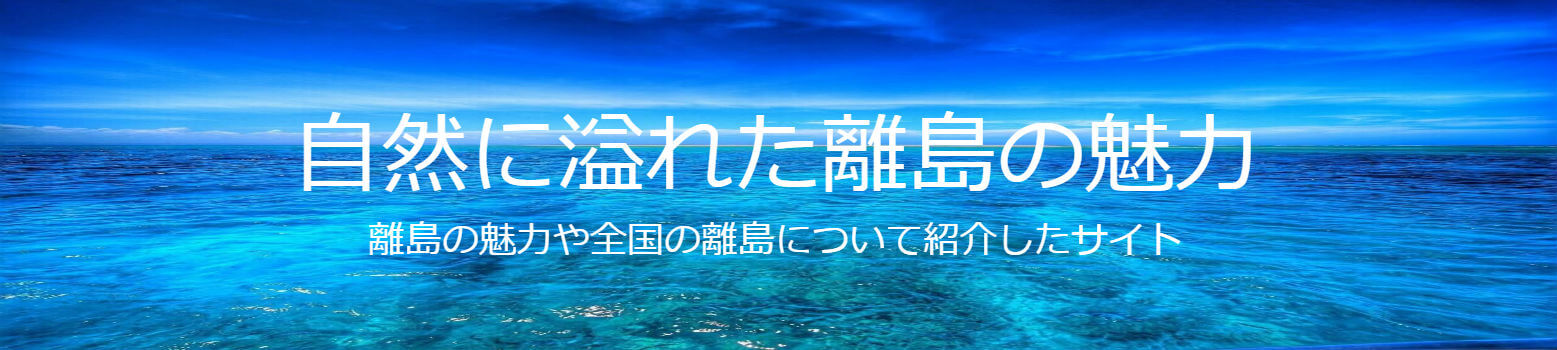離島とは何か、その定義とは
日本も島国、つまり島となりますが、島とはどういう定義なのか、これもちょっと知識として理解しておく方がいいでしょう。
島というのは国連海洋法条約によって定められています。
そこを見ると島というのは、自然に形成された陸地、水に囲まれており、高潮でも水面上にあるものです。
こうした定義に当てはめてみると、高潮の際に水面上にある島は日本国内に数万単位といわれています。
この定義ではなく、海上保安庁の海上保安の現況では、北海道、本州、四国、九州等日本国内に鋼製されている島の数は6852という発表です。
保安庁で行っている島は、周囲が100m以上あるものとしています。
本土と橋、防波堤等細い構造物でつながっている場合には「島」とし、橋や防波堤などとは違い幅広くつながり、本土と一体と見えるものについては除外、さらに埋め立て地についても、島としていません。
日本国内にある島、その構成について
海上保安庁のいう島、6852の島を詳しく見てみると、都道府県庁所在地の島は「5」あり、無人離島は「6430」、さらに有人離島、つまり日本の国民が居住している島は「417」、内水面(湖)に存在する有人の離島が「1」となっています。
無人離島は北方領土、竹島、尖閣諸島を含む6430以外に、周囲100m未満の沖ノ鳥島など無人離島が存在しており、内水面にある有人離島は滋賀県にある沖島です。
普段意識していませんが、日本国内で最も広い面積を占めているのは「本州」、次に北海道、九州、四国となります。
そう、日本は島国なので、普段は全く意識していませんが、私たちは島に暮らしているということになるのです。
四国の次は択捉島、国後島、そして沖縄島とつづきます。
普段、島とつけて呼ぶことがない沖縄も島、その離島に石垣島、竹富島、西表島などがあるわけです。
離島のこと、こうして調べてみると「ああ、そうか」と思うことばかりで、普段島にいるということを意識していないせいか、納得できることが多いのです。